DNARとは
DNARとは、”Do Not Attempt Resuscitation” の略で、心停止時に心肺蘇生を行わないことを意味します。医療現場ではよく使われる用語ですが、正しく理解していない医療者も多いのではないでしょうか。「DNARだからICUには入れない」「DNARだから気管挿管はしない」は間違った使い方です。私自身も研修医のころにはきちんと理解できていませんでしたが、医療者として正しく理解しておかなければならない概念ですので誤解しやすいポイントをまとめます。
① DNARは心停止時のみに適応される
まず、重要なポイントはDNARは心停止時のみに適応されるということです。例えば、市中肺炎で入院した患者さんが、入院後に呼吸状態が悪化してリザーバー10L/minの酸素投与が必要になったとします。この場合、心停止には至っていないので、事前にDNARを確認していたからといって気管挿管をしないということにはなりません。気管挿管をしないという希望がある場合にはその旨を別途で記載しておく必要があります。同様の理由で、DNARだからICUに入らない、透析をしない、などは間違いです。
② 予期された心停止には心肺蘇生の適応はない
もう一つ、誤って認識されやすい点として、癌の終末期など心停止が予期され心肺蘇生をしても回復の見込みが100%ないと判断した場合は心肺蘇生はやってはいけません。このような場合には、DNARを一つの選択肢として提示するのではなく、DNARの方針にすることをご家族に説明しなければなりません。ご家族の中には心肺蘇生は当たり前にやるべきもので、やれば回復するものだと思っている方もいます。しかし、人はいずれは亡くなるものであり、医療の力で永遠に寿命を延ばせるわけではありません。人生の最期の時間は家族に見守られて手を握られながら静かな場所で過ごしたいと思う人が多いのではないでしょうか。回復の見込みがないのに心肺蘇生をやることはその時間を台無しにして患者さんに危害を加える行為に他なりません。
③ 目的を意識する
「高齢だからDNARをとらないと」などと言っている人がたまにいます。そもそも、コードステータスを確認する目的は、それぞれの患者さんの価値観にあった医療を提供することです。人によって価値観は様々で、人工呼吸器が外せない状態になっても家族と筆談でコミュニケーションがとれたり、好きなテレビ番組がみれたらそれでいいと考える人もいれば、自分の身の回りのことができないのであれば死んだ方がましだと考える人もいます。
医師としてやるべきなのは、「高齢だからとにかくDNARをとる」と短絡的に考えるのではなく、どれ程の確率で患者さんが許容できるADLまで回復するのか、また蘇生処置やその後の治療がどのように辛いものなのかをできるだけ正確に情報提供することではないでしょうか。「やってみないとわからない」というのはその通りなのですが、そう言って判断を患者さんやご家族に丸投げするのではなく、一番よい選択肢をとれるように一緒に悩んで考えられる医師になりたいと思います。
どんどん医療が進歩していき、最先端の治療・研究が行われている一方で、救えない命もたくさんあります。病気を治すことだけを考えてしまうと、このような救えない患者さんやそのご家族の気持ちは置き去りになってしまいます。現代の日本の医療現場においては特に、最期の時間をいかに質の高い時間にできるかどうかも考えながら日々の診療をすることが大切だと思います。
〈参考文献〉
終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで現場とともに考える

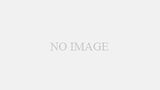
コメント