悪性胸膜中皮腫の症例を経験したので、研修医や専攻医向けの一般的な内容をまとめます。
概要
- 中皮腫の発生は胸膜が最も多く、その他に腹膜や心膜、精巣鞘膜にも発生する
- アスベスト曝露が原因の1つとされるが、アスベスト曝露がなくても発症した例もある
- 長期のアスベスト曝露がある場合の発症頻度は約5%
- アスベスト曝露開始から発症までの潜伏期間は25~50年
- 組織型には上皮様(約60%), 二相性(約20%), 肉腫様(約20%)があり、肉腫型が最も予後不良
検査・診断
- 造影CT:胸水貯留や胸膜肥厚が高頻度にみられる。より悪性を疑う所見として、①肺を取り囲む全周性の胸膜肥厚、②結節状の胸膜肥厚、③厚さが1cmを越える胸膜肥厚、④縦隔胸膜の肥厚が挙げられる。
- PET-CT:遠隔転移の評価に使用する。
- 腫瘍マーカー:血清の可溶性メソテリン関連ペプチド(SMRP)、オステオポンチン、胸水中のヒアルロン酸(カットオフ値は100,000ng/mL)がある。あくまで診断の補助に使用する。
- 生検:確定診断に使用する。生検には経皮的針生検、内科的局所麻酔下胸腔鏡下生検、外科的全身麻酔下胸腔鏡下生検があるが、基本的に外科的全身麻酔下胸腔鏡下生検が推奨される。局所麻酔下胸腔鏡下生検は胸膜中皮腫の診断には有用であるが、亜型までは診断できないことが多い。
- 病理診断:しばしば上皮様中皮腫と腺癌の鑑別が困難な場合があり、その際には免疫組織化学を参考にする。上皮様中皮腫の代表的な陽性マーカーとしては、calretinin, WT1, podoplanin(D2-40), HEG1, keratin5/6(CK5/6)が挙げられ、陰性マーカーとして、claudin-4, CEA, TTF-1, napsinA, BER-EP4などが挙げられる。
治療
- 外科的治療:根治術には胸膜切除/肺剥皮術(P/D)と、胸膜肺全摘術(EPP)があり、臨床病期や組織分類によって手術を行うかどうか検討する。(一般に手術が考慮されるのはstageⅠ-ⅢA期。組織型は上皮様>二相性>肉腫様の順に手術成績が良好。)
- 周術期化学療法:切除可能な症例に対して術前または術後にシスプラチン+ペメトレキセド併用療法の実施を考慮する。ただし手術加療単独と手術加療+術前/術後補助療法を直接比較した試験はなく、術前/術後のどちらに行うべきか検証した前向き試験もない。
- 放射線治療:胸膜肺全摘術の術後後に片側胸郭照射を考慮する。胸膜切除/肺剥皮術の術後や手術適応のない症例には放射線照射は推奨されない。
- 内科的治療
PS良好例(PS1-2)の一次治療ではニボルマブ+イピリムマブが第一選択※1。他の選択肢としてはプラチナ製剤+ペメトレキセドを考慮される。またプラチナ製剤+ペメトレキセドにはベバシズマブの併用※2や終了後のゲムシタビンによる維持療法※3も検討される。
PS不良例(PS3-4)では化学療法は推奨されない。
二次治療以降はニボルマブ単剤>ペメトレキセド単剤、ビノレルビン単剤、ゲムシタビン単剤、ビノレルビン+ゲムシタビン併用を考慮する。
胸膜中皮腫の補償・救済制度について
アスベストの吸入によって発症する指定疾病※と診断された場合、「労働者災害補償保険制度」と「石綿健康被害救済制度」の2つの救済制度があります。補償制度については医者が知識不足になりがちな部分ですが、知らないと患者さんの不利益になるので必ず知っておきましょう。
※中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うアスベスト肺やびまん性胸膜肥厚
労働者災害補償保険制度
- 仕事が原因ででアスベストに曝露され、胸膜中皮腫を発症した方への救済制度
- 給付内容は療養給付、休業給付、疾病年金、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭料など
- 最寄りの都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせて認定を受ける必要がある
石綿健康被害救済制度
- 上記の労災保険の対象にならなかった方への救済制度
- 給付内容は医療費、療養手当、葬祭料など
- 最寄りの保健所や地方環境事務所に申請請求を行う
参考文献
- 肺癌診療ガイドライン2024年版
- 日本肺癌学会ホームページ
Q82救済制度があると聞いたのですが,申請の手順などを教えてください

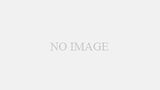
コメント